👻
「幽霊なんていません。」
我妻俊樹『奇々耳草紙 死怨』(竹書房 2016年)の話をさせて下さい。

【概要】
人気シリーズ最新作。頁をめくる手を止めてふと、周りを見渡すと、何かが変わってしまったような気がする・・・・・・よじれた恐怖がまとわりついてくる!金縛りの自分を見下ろす人達、見知った顔があったので声を掛けたら・・・・「取り囲まれて」、陰惨な事件により弟を亡くした男のもとに届いた奇妙な葉書「蛇長蛇男」など、日常に仕掛けられた黒くて奇妙な罠の数々、怒涛の61篇を収録!
裏表紙より
【読むべき人】
・少し不思議系の実話怪談が好きな人
・サラサラ読める実話怪談が好きな人

【感想】
実話怪談って怖さよりも、アイデア・文体が勝負だと思う。
ネットが普及しSNSも普及した現在、アマチュアのネット怪談なんて手を伸ばせばひょいっ!!!と読める。Twitter等のSNS、小説投稿サイト、「死ぬほど怖い話を集めて見ない?」兼まとめサイト、SCP財団、個人ブログ・サイト・・・等々。
でもその多くが、どこかで読んだことあるような話だったり、大して怖くなかったり、もう一行読んだだけで全部わかったり、そもそも文章がめちゃくちゃ読みづらかったりする。全然怖くない、いや私の方が多分巧く書けるわ。とか場合によっては思ったりすることも多々。実際に書けるかどうかはともかく。
体感でいえば、玉石混合という四字熟語があるが、ネットに蔓延る怪談は玉石石石石石石石石石石石石石石石石混合くらい。
玉は梨.psd先生とか。あと工作力でいえば雨穴さんとか(ただし雨穴、文章力おめー、だめだ)。単品でいえば「夜明け望遠鏡で景色見てたら猛ダッシュ&猛ピンポンしてくるヤツ」とか。「あなたの娘さんは地獄におちました」。
石でいうと、Twitterにあがる「ツイート怪談」とか。体感として、Twitterに上がる怪談は99%クソ。総じてクソ。本当にクソ。文字数の制限が厳しい為と思われる。
そこを逆手にとり、優秀な文字数制限怪談のみを書籍にしようという「#10文字ホラー」という取り組みがありましたが、あれは凄いと思ったね。本パラパラ見たらやっぱ全然違うもの、クオリティ。僕も一作掲載されましたが。
閑話休題。
まぁともかく、ネットには怪談が多く蔓延っているけれどもその9割がしょーもない怪談ばかりである。
だから僕達は、実話怪談本にこうして金を払って読む。今までない怪異を読むために。出来れば読み易い文体で。
時間は有限なのである。面白い怪談が一気に読めるのであれば500円600円なんて僕達にとっては実質無料も同然なのである。
嘘。さすがにちょっとそれは高いので、中古で買っている訳ですが・・・でもそれは僕が月々12万円のフリーター(ひとりぐらち!!)だからであって・・・赦してくれ・・・赦してくれ・・・。
発想、読み易さ。その二つを我妻氏の怪談はひょーいと軽く凌駕する。肌をなぞる冷たい感触。
特に発想。怖い、よりかは不思議。謎。不条理。どういうことなの・・・?となる感覚がたまらない。いやまぁ実話怪談なんで発想ではなく、実際に起きていることなのだけれども・・・言い方難しい。集めた事象が面白い、が適切な表現だろうか。
文章も確かに稚拙な部分は見られるけれども、詩的表現がベースになっているからかすらすら入ってくるし読み易い。日本語が破綻していない、ネット怪談あるあるの不自然な接続語・助詞が一切ないというのもポイントが高い。
文章に関しては、あとバランス感覚がいいと思う。実話怪談は単行本化されているものでも、多少「前半のここの説明いらんだろ」とか「オバケの出番少なすぎ」等あるのだけれども、我妻氏の怪談に基本そういった不満を抱いたことは無い。きちんと読み返しやってんだろうなぁ。
あー。しゅき。我妻氏。しゅきしゅきしゅきぴ。我妻氏。
そんな感じで一気読みしている全5巻のシリーズであるがあっという間に4冊目、という事実に震えがとまらない・・・。もっとずっと読んでいたかったんですけどね・・・。
四巻にあたる本書は、三巻とは違って一巻二巻同様60篇以上収録されている。ただ怖さでいえば・・・後半に良質なものが偏っているかなあ、という印象。そこは三巻と同じかな。

以下簡単に面白いと思った実話怪談のあらすじと感想をネタバレ恐れず書いていく。
好きな話は「幽霊はいません」「老人会」「秋分」
「秋分」pp.129-131
出勤前に一時間ほどランニングをしていたが・・・。
〈はまもとしんいち 6さい〉p.130
何とも不気味な一編。まずひらがな・本名・年齢っていうのがもう気持ち悪い。
こういう時、日本人で良かったなぁと思う。英語圏だったら「HAMAMOTOSHINICHI 6years old」である。全部の文字がアルファベットだと恐怖感が薄まる。子供がまず初めに使う文字「ひらがな」で書かれているからこそ、不気味さが一層増すのである。
「行旅」pp.132-141
勝間さんの叔父は各地を転々として暮らした人で、仕事も定まらずホームレスだったこともあるらしい。p.132
実話怪談、というかもはやロードムービーである。何年もかけて、叔父がいろんな場所に住んで働いて働かなかったりして・・・を繰り返している合間に、かつてアパートの隣室に住んでいたNさんという男の幻影を見たり見なかったりする話である。
東京や日本海側の地方都市、更には違う街・・・で暮らす叔父を読んで、ああ人生って旅なんだなぁ・・・と思う。一人きりの旅。故郷が故郷でないこと。筒井康隆先生の「旅のラゴス」を思い出す。
同時にクライマックス、残り3ページにかかる不穏な畳みかけは見事で、最後は何ともいえない後味が胸に広がった。
「掴む手」pp.156-157
咲希さんは右手が子供の頃のけがの生でうまく曲がらないが、時々人の服を無意識にぎゅっと握っている。
咲希さん「嫌な話でしょ、でもこれって二つの考え方ができるんだよね。死が間近に迫っている人に、この手がいわば告知をする役目を果たしているのか、それとも・・・」p.157
右手は、死を告げるのか。それとも・・・。
咲希さんにとってはどっちでもいいかもしれないが、身近な人にとってはどっちでもよくない話である。後者だったら今すぐ関係を断ちたい。ラインをブロックしたい。「知人」から「かつての知人」へとなりたい。絶縁したい。同じ家は愚か同じ町に暮らすのは嫌だ。絶対に引っ越したい。結婚おつきあいデートはおろか「お友達から」でもお断りしたい。
へらへらしてないで早く神社か寺行って直してもらえや案件である。それを放置している地点で咲希さん自身も無邪気な死神にすぎない。
ちなみに最後の一行が素晴らしい。
話を聞きながら思わず、手の届かない距離まで後ずさってしまう。p.157
「やつれゆく息子」pp.170-172
離れて暮らす息子が、仕事の配達中に追突事故を起こして入院した。
妻「ちょっと何で人違いしてる訳。自分の子供の顔もわからなくなったの?」p.171
衝撃的な展開でちょっとビックリした。
母親が肺癌なのもあって、入院時はよく見舞いに行っていた。ナースステーションで部屋がどこかを聞くのである・・・自分の体験と近くて、その分生々しく感じられる。
よく、家族・特に兄弟姉妹に怪異現象がわあっ・・・!!と起きて、「それ以来兄は顔が変わったままだ」「それ以来姉は別人のままだ」と締める実話怪談があるが、それの発展したパターンと言えよう。よりリアルに肉薄しているというか。
ちなみに、実話怪談あるあるとして挙げられるのは、兄入れ替わりがち。兄が7割父母2割残り1割・・・な気がする。少なくとも入れ替わりを体験するのは子であることが多く、体験者が父親のパターンはなかなか珍しい。
「知らない女」pp.173-177
女の飛び込み自殺を見た夜に、見知らぬ女が訪問してくる。
一瞬駅のホームで見た光景が蘇るが、もちろん外に立っているのは列車に飛び込んだ女ではない。p175
じゃあ誰だよ。
そこはむしろ朝飛び込んだ女性が、夜部屋の前血まみれで突っ立ってるのが実話怪談の「もちろん」だろ。と思わないでもないが・・・その女の行動とオチが不気味で印象に残った。
要するに生霊が、マネキンに乗り移ったってことなのだろうか。呪い?
それとも、最後の一行から鑑みるに、別人と見せかけて飛び込んだ女性と夜に来た女性は同じ人だったのだろうか。
どうとでもとれるし、どうとでもとれない。
あと女×マネキン、だとあれ思い出した。「探偵ナイトスクープ」のマネキンに恋した女性とかっていう事件。確か後日訪問したら普通に結婚しててどうしてあの時マネキンを識別で来たか分からない・・・という話。
等身大の人形ですからね、マネキンって。
「老人会」pp.186-187
東日本の観光地に住んでいた女子小学生だったサチさん。下校中、突然知らない老人たちがカメラをむけてシャッターを切ってきた。
まるで動物を撮るよな不躾さに腹が立ったので睨みつけたところ「田舎の子は目つきがきついねえ、怖い怖い」と、聞こえよがしにつぶやいて老人たちは行ってしまった。p.186
後日土産屋の店員に効いたら、そんな老人達なんて実在しないですよ。くらいなオチかなぁ・・・と思ったら予想の斜め上を行くオチでよかった。まさかのスカッとジャパン系実話怪談だった。
でもそれを凌ぐのは、「うわぁ・・・」という恐怖。
多分体験者になったら間違いなくその夜は眠れない。し、一生のトラウマ必至。
すっきりと、うわぁ・・・。何とも言えない唯一無二の後味。
本書で二番目に好きな一篇。
「幽霊はいません」pp.193-198
家族が経営する事業の一つである遊園地に、小学生の頃はよく友達を連れて行った。なかでもお化け屋敷は本物の幽霊が出るという噂があって・・・?
女「残念、幽霊なんていません。あれは機械で動く人形なんですよ。それだけがあって、後は何もありません。幽霊がいるですって?とんでもないですよ、幽霊なんていませんから」p.196
不気味な女が出てくる一篇。お化け屋敷に行った小学生に対して「幽霊がいない」としきりに繰り返す様が、目に浮かぶようである。ファッションについても詳しく言及されているから、より生々しい。同時に、生きている人なのか?頭がパアになった人なのか?とも思うが、どうやらそうでもないらしい?では一体彼女は何。子供にしか見えないような存在ではあるが、目的自体も謎。なんのためにそこにいるの?そこで死んでたり近くで惨殺されてたり自殺してたりとかなら分かるがそれが一切ないということは、存在の母体は一体何。幽霊を否定したい存在といえば、やはり終盤で描かれているようにお化け屋敷の人形の幽霊なのか。いやそれだったらあの詳しいファッション描写は何だよ。デニムスカートとか、スニーカーとかどこで買ったって言うんだよ。ABCマートか?
口調も妙に癖になる。「幽霊なんていません」強めの断定の敬語は読んでいて、まるで耳に聴こえてくるかのよう。沢城みゆきくらいのアルトの無機質な声で聞こえた。「は」ではなく「なんて」と言っているのが良い。
この女のキャラクターがばっちりたっている、実話怪談。キャラクター小説という言葉があるが、これはキャラクター実話怪談。あの「猛ダッシュ&猛ピンポン野郎」と張れるんじゃないか。あわよくば、付き合ってほしい。
本書で一番好きな一編。

台所に置いて、普段のメメントモリは僕はこれですましてます。
感想を述べる前に、我妻先生の作品について日本が「一部稚拙な部分はあるが、」と述べた。本書ではそれが明確に示された一篇がある。
「夜を明かす」pp.178-182におけるp.179の描写である。頁前半では、出てくる人影は主人公のいるビルの、隣のビルの屋上にいたことになっているが、頁後半では「屋上に戻ると」と書かれていてその後主人公に接近している。主人公と同じビルの屋上にいたことになっている。また、人影の行動の描写があるが、何故かこの一篇だけ妙に下手。全然何しているのか分からない。
恐らく、本書自体締め切りにかなり追われた一冊ではないのかと推測する。
61篇収録されているにも関わらず、印象に残った話数は45篇収録の3巻より少ない。なんか知らんが、我妻氏にしては無味乾燥な実話怪談が前半ならなんだ印象。妙に詩的で不思議さがウリだから、湿り気が無いと何も心にこないのである。

以上である。それでも4巻も比較的面白く読めた。
次は5巻・・・最終巻である。気合を入れて感想記していこうと思う。
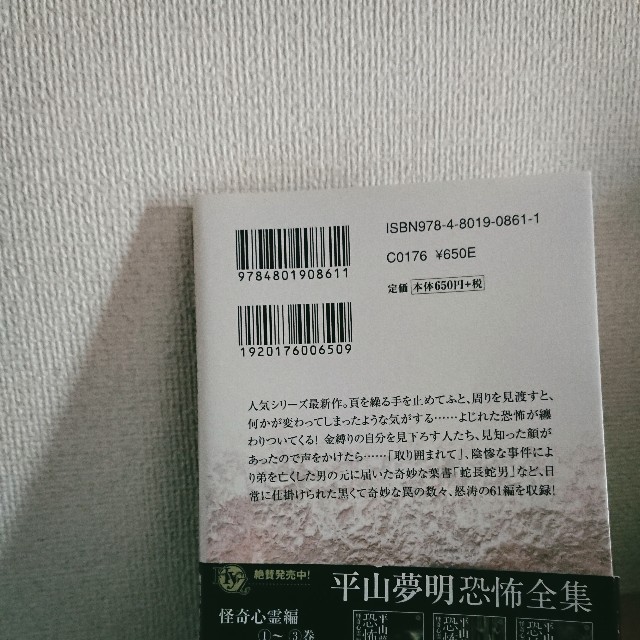
***
LINKS
しりーず。「見て下さる方の中には実話怪談本とか興味ない方もいるのかなと思って違うジャンルの本載せようと思うけれども、ついついめんどくてずるずる同じシリーズを連打して投稿してしまう」病にかかっております。どうやら不治の病らしいです。助けて。
名著なので事あるごとに思い出す。4年前に読んだ本だけれども、今でも明確に思い出せるよ。
20220420 相も変わらず、昔描いた記事のを編集したものである。
今思うと、「幽霊なんていません」は、早見沙織でもいい気がする。