家庭をもったばっかの僕らのささくれは。
窪美澄『水やりはいつも深夜だけど』(KADOKAWA 2014年)の話をさせて下さい。

【あらすじ】
幼稚園を出て小学校に通い中学受験をし大学までストレート。
マンションで専業主婦をする主人公だったが、
息子・有君の通う幼稚園には、
普段から素行不良が目立つ拓斗君がいて・・・。
彼の母親はここでは珍しく、パートをしているという。
子どもがいる家庭の、
心のささくれを緻密に描く、
5の短編。
【読むべき人】
・幼稚園児、保育園児が家族にいる人
・家庭を持ったが、親になり切れない人
・親になったばかりの人
・新婚の人
【感想】
ダ・ヴィンチに紹介されていて、
それからずっと気にはなってた短編集。
この度無事図書館で見つけてこれはこれはと手に取った。
本作は表紙の幼女の写真(これめっちゃいい写真だよね)
からわかるように、
幼児がいる家庭が主題となっている。
同時にタイトルの「水やり」からわかるように、
各話それぞれ植物と絡められている。
結論、
いい小説だなーと思った。
普通幼児教育っていうのは余裕がないものだし大変なものだしドタバタするものなのだけど、
今作も確かにそうなのだけど、
重視されているのはそこじゃない。
植物のように、静かに、
心の奥底でささくれ立つ感情の機微を丁寧な筆致で描いている。
あんまこういう作品ってなかったと思う。
まぁ僕本の虫、ってほどの人ではないのだけれど。
I like dokusho.NO,NO,LOVE,
まぁともかく、
「話題」作になるのがよく分かる。

すげーいい表紙だと思う。
以下簡単に。
一番好きな話は「砂のないテラリウム」。
浮気する男はバカではない。
寂しいのだ。
「ちらめくボーチュラカ」
:息子が仲良くなった拓斗君の家庭は高級住宅街とは一線を画しているようで・・・
所謂高級住宅街の話である。
・関東住み
・親がちょっと裕福
・中学から私立
・20代半ばで結婚し寿退社
・習い事をしつつ育児に優雅に勤しむ
はえ〜。
疎遠である。
もうだめ。まず静岡市に生まれた地点でもうアウト。
でもこういった人達はまじで、いるのだ。
関東の私大行ってたけど異文化。
恵比寿住み、中学からカリタス、マンションのゲストルームでこんどあそぼうよ・・・。
しかも彼女達にはその自覚がない。
仰天驚愕ひっくり返りそうだったけど、
ぎりぎりかくして
「いいね、いこうよ、ゲストルーム」
ただそんな主人公も実は僕(静岡市)に近い人間である。
幼少期は田舎で過ごしていたが、イジメに合い、
そこから顔色をうかがいながらママ友との「友達」でいなくてはならない。
難しいよな。
難しいよ、と思う。
上記に述べた恵比寿、カリタス、マンションとは僕も「友達」であるけれど、
心の奥底から「友達」かというと怪しい。
嫌いではない。
面白いと思う。
卒業旅行も一緒に行ったし、
今でも飲もうと思えば飲めるけど、
やはりどこか心を底から開けないのはやはり環境の違いなのか。
幼児には、この壁がない。
題名の
近づこうよ。仲良くしようよ。
「人間関係の一歩」を表現しているように思う。
境遇に一番共感で来たのは本作かな。
ちなみに、この作品読んで思い出したのが、
貫井徳郎『愚行録』
「サボテンの咆哮」
:仕事から帰る時間が遅いなか、二世帯住宅の話があがり・・・
父親の話。
なんか珍しいなって思った。
女性作家のこういう短編集って、たいてい一貫して女性が主人公なものだと思っていた。
けれど、
もう視点が全て父親側、
日本全国の専業主婦がこれを読めばいいんじゃないかなとすら思う一遍。
サボテンは、「仕事で忙しい父親(主人公)」のことだろう。
終盤、タイトル通り彼は咆哮する。
それに傷ついた妻が、ショックに打ちのめされながらも、
最後、
「だから、これから、いろいろ話したいの、あなたと」p.97
話し合おうと言っているのが良かった。
ある意味、育った環境を話しながら超えていこう、
という点では「ボーチュラカ」と同じなのかも。
個人的にこの短編の帰省するシーンがすごく好き。
家庭と仕事の挟み撃ちの主人公の疲労と、
下町の雰囲気がよく混ざっていて良い。
「ゲンノショウコ」
:他の子と比べてマイペースな娘・風花がどうしても気になり・・・
障がい者、(もしくは発達障害)疑惑がある子供の家庭を扱った作品である。
ゲンノショウコの花言葉は「憂いを忘れて」
主人公は障がい児の妹と共に育つ。
だからこそ、娘のマイペースに過敏になる。
彼女は将来生きていけるのか・・・?と不安になり、
ママ友から「厳しすぎのでは?」とひそひそされてしまう。
そんな彼女に、
終盤、
無邪気に微笑む娘・風花。
「憂いを忘れて」
ちなみに今作だけタイトルとなる植物が出てきてない。
娘の名前、風花。
花。
ゲンノショウコは「娘自身」、ということなのだと思う。
今作では、障がい児の息子をもつ桜沢さんという人が出てくる。
一番印象に残った人物。
障がい児の母親で苦労もしているはずなのに、
同級生の母親からみて一段と輝いて見える。
どんなに輝いて見える人でも同じく苦労があって大変なのだ。
それでも快活に生きるから彼女達は「輝く」のだ。

「砂のないテラリウム」
:準備もしないまま授かり婚をし、妻は藍の世話をみているが俺は・・・
これも珍しく父親主人公。
浮気の話。
僕はこの話が一番好き。
「ポテトチップスを食べて。歯磨きをしないまま寝てしまうこともあった」p.148
長い交際の末心の準備もないままにできてしまい、
不安いっぱいの妊婦であった妻は、
産んでしまうとたちまち「母」になる。
ずっと娘を見ている。
興味を持ってもらえないことに、
また「父親」という立場に慣れないうちに、
寂しさを感じながらもふらりと浮気をしてしまう。
その過程の生々しさたるや。
けれど勧善懲悪、
浮気は人を傷つける。
テラリウムというのは植物名でない。
雑貨店などで見ることの多い、
苔の生えた球体のこと。
「閉じられた瓶の中で、苔は勝手に成長していた。苔そのものが呼吸をしているせいなのか、瓶の内側に細かい水滴がついている。それが息苦しさを感じさせたが、それでも苔は生き生きとした緑色を保っていた」p.185
テラリウムは「家庭」。
砂のない、とあるように安定はしていないし、
息苦しくも感じる時はあるが、
生き生きとそれは大きくなって育っていく。
その存在をまじまじと眺めた主人公は、
この日をきっかけにやがて「父親」になっていくのだろう
結婚したからといって、
夫ではない。父親ではない。
一人の男でありたい。
そういった男性側を、
いやみなく下品でなく
けれど男性をけなすこともなく、
真摯に見つめる作者のそのまなざしが、
とてもいいなと思った。
「かそけきサンカヨウ」
:女子高生の陽の父親が再婚して、4人家族になった。
幼児を連れ子にもつ女性と父親が結婚した。
別に、その二人が嫌いなわけではない。
家事をこなすことに抵抗があるわけではない。
けれどなんとなく居場所がない。
女子高生が主人公。
サンカヨウは主人公の「親しく思う気持ち」。
母親が描くサンカヨウの絵を主人公は大事に持っている。
けれどそれはかそけき。
決して表立つような感情ではない。
かそけきサンカヨウ。
終盤、義妹となるひなたちゃんに主人公が大きい声をだすシーンがある。
怒る。
けれどその感情の爆発を経て初めて、
彼女達は「家族」になったのかなと思う。
テープでつぎはぎされたサンカヨウのように。
あと女子高生のくせに彼氏つくってんじゃねぇ。爆発しろ。
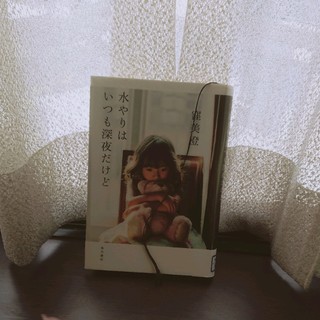
以上である。
どの短編もうまく植物が繋がっていたように思う。
表紙の女の子のように、
どこかうつむいてしまう心情を深夜、静謐に、切り取る。
水やりはいつも深夜だけど。
この小説は子供を持った時こそ返し読みしたい。
まぁ・・・
子どもはおろか、
結婚はおろか、
就職できるかどうかすら怪しいわけですが・・・。